はじめに
概要
贅沢なチーズ鱈、卵の黄身をとろっと絡めたトースト、はんぺんのオイルフォンデュ、白砂糖入りの七草粥、ハーブティーで淹れたココア、モンゴルのいのちを頂くヤギのシチュー……20人の作家が自分だけの“ご馳走”を明かす。読めば「美味しい!」を共感できる極上のエッセイ集。
この本を、わたしは一体いつ読んだのだろうか。手元の文庫本には「2011年2月28日 第一刷発行」と書いてあるので、たぶん10年以上前、高校生の頃に買って読んだのだろう。その頃のわたしといえば、『恩田フリーク』と言っていいほど恩田陸さんの作品を読み漁っていたので、その延長線で手に取った一冊だと思う。
この本はもともと、朝日新聞で連載されていた食に関する作家さんのエッセイ各4編ずつをまとめたものらしい。
20人の作家さんが書いている食のエッセイが読めるが、どの作家さんが綴るエピソードもとても素晴らしく、食欲を掻き立てられるものばかり。文章を書くことを職業にしている方々は、本当にすごいなあと敬服する。
大好きな恩田陸さんのエッセイはもちろん、ほかにも名文がたくさん読める。
感想
「列車でビール 長旅には酒器を連れて」
旅の始まり。列車に乗って席に落ち着き、プシュッと缶ビールを開ける瞬間に優る幸福を、ちょっと思いつくことができない。
この席に辿り着くまでには多大な労力を払っているので、より一層、今ここに確保した席と確保された時間にじわっと嬉しくなるのだ。
P16「列車でビール 長旅には酒器を連れて」恩田陸
この本を最初に読んだのはたぶん高校生の頃で、その頃はここに書かれている気持ちがまだわからなかった。なんたって未成年なので。でも、今読み返すと、ものすごくものすごくこの気持ちがわかる。
わかるようになっている。
わたしはお酒が全然強くないので、ビールの美味しさがわかったのも最近なのだけれど。
本を再読する喜びは、こういうところにあると思う。
わたしは特に、一番熱心に本を読み漁っていたのが学生時代なので、その頃にはまだわからなかった気持ちや考えがたくさんある。だからこうやって以前好きだった本を再読することにして良かった。
少しずつ、まだまだだけど、それらを書いていた作家さんたちの当時の年齢に近づいていく。
本は、一生自分の傍にいてくれる、何度読み返してもいい、心強い存在だなあと改めて感じている。
ああ、さっそくチーズ鱈が食べたくなってきてしまった。好きな文章を読むと、すぐに感化されてしまう。
「うたれる店」
個人的には、津村記久子さんの「うたれる店」がとても好き。そのなかから少しだけ引用させてもらおう。
もう今月の出来事はこれだけでいいとすら思いながら、至福に浸ったあと、なぜかすぐにそわそわし出してしまう。わたしがお茶屋に入る時は、基本的に分の仕事をするためだが、これだけのものが×××円でなんてなあ、いい世の名だなあ、と思い始めると、とたんに恐縮してしまって、仕事どころではなくなるのだ。なんだか試されているような気分になるのだろう。いいのか、わたしはこんなにちゃんとした店で、リラックスではなく仕事をしようとしている。それは正解なのか。
P139~140「うたれる店」津村記久子
ここでは、津村さんが素敵なパン屋さんに出会った時のエピソードが書かれている。
パン屋さんやカフェのことを「お茶屋」と書く感性が大好き。
全編を通して、思わずうっとりしてしまう文章なのだ。そして、ここに書かれていることはかなり共感できる。わたしも仕事や自分のしたいパソコン作業をするためによくカフェを利用するけれど、リラックスするためにカフェを利用しなくていいのか、こんな自分の仕事部屋みたいにして。と思うことが少なくないからだ。
仮に目の前に「仕事・勉強用席」と書いてあったとしても、なんとなく罪悪感がある。だからそういう言葉にしづらい感覚を文章化している津村さんのエッセイに心うたれた。
「うたれる店」というタイトルもとてもいい。
津村さんは実際、食べ物のことを書くのが好きとも書かれていて、勝手になんだかうれしいきもちになる。「食べ物よ!」というエッセイでそのエピソードを読める。ほんとうに面白い。すごい。語彙力がなくなってしまう。
「いとしの自作味噌汁」
「いとしの自作味噌汁」というエッセイもとても好き。
今年に入ってからはずっと平日は外食している。それでべつにいい。どのお店にも納得して入っている。晩ごはんを食べるとほっとする。一日会社で仕事をして、直立歩行できるだけの、そこらじゅうの筋肉が凝り固まった軟体動物のような、寄る辺ない生き物になってしまった状態を、ちゃんと人間に戻してもらえたような気さえする。
P149「いとしの自作味噌汁」津村記久子
なんて素晴らしい文章なんだろう。ひっくり返ってもこんな文章を書けるようにはならないと思う。こんな表現力を身に着けるために、津村さんの行かれている飲食店に片っ端から入ってみたくなる、そんな衝動に駆られるほど美しい文章。
わたしもこんなふうに、外食も自炊ももっと純粋な心で楽しめる人間になりたい。
「どのお店にも納得して」入るような人間に。大げさかもしれないけれど、このエッセイを読むと、そんな気持ちになるのだ。
「ほめ言葉 おいしいものを食べるわけ」
江國香織さんの「ほめ言葉 おいしいものを食べるわけ」も大好きなエッセイだ。
今まで人生のなかで読んだ、食にまつわるエッセイのなかで一番好きかもしれない。というか、江國香織さんのエッセイはどれも本当に大好きなのだけれど。彼女の物事や、世界をみる視点がとても素敵で、読んだあとは明るい気持ちになれるから。
わたしも「いつか来る日」のために、一生懸命おいしいものをちゃんと食べよう。毎日食べるものを大切にしよう。ここに書かれているのは、特にそう思えるエッセイ。
そういえば最近、この本に収録されているエッセイがSNSでバズっていた気がする。
バズっていたのは新聞記事だけど、読んだことのある文章だ!と思って少し興奮したから。中村文則さんの「命の糧 フリーターの時」というエッセイ。
これを読むと、ドトールコーヒーに行きたくなる。
これを再読した影響で、実は一昨日、ドトールコーヒーでレタスドックを頼んだ。ものすごく久しぶりに。変わらずに美味しい味だった。また食べたいな。
わたしは食に関する漫画も好きだし、物語も好きだし、食にまつわるエッセイも大好きだ。
実は、少しだけ食に関して苦手意識があって、自分は食事が上手じゃないと前から思っている。自分から積極的に、美味しいごはんを探し求める欲求が足りない気がしている。
毎日、ひとり暮らしで四苦八苦しながら食事を摂っている節がある。
好き嫌いはなく、小さいころから何でも食べられるし、なんでも美味しいと感じられるのだけれど、食事を摂るのが億劫で、作るのも得意じゃなくて、食べるのも下手くそ(よくこぼしたりする)。
手に力が入っていないのか、箸もすぐ落とす。
だから、食事が大好きな友達たちにはいつも救われている。
一緒に美味しいごはんを食べてくれてありがとう、わたしを美味しいごはん屋さんへ連れだしてくれてありがとう、と心から思っているし、尊敬している。
なんとなく食事を上手く摂れない、という苦手意識を持っているからこそ、殊更にこういうエッセイを読むのが好きなのかもしれないなあと思う。
脳内で想像力を搔き立てて、美味しいご飯を一緒に食べている気持ちになれるから。あと、他の人達がどのようなスタンスで食事というものに向き合っているのかを垣間見れるから。
再読してみて、そんなことをつらつらと考えた。2024年の新年が明けてすぐくらいの今日。
わたしのご飯
ちなみに、今日の夜ご飯はセブンイレブンで買ったラーメンサラダと明太ポテサラ(とっても美味しかった)。
そして、欠かせないのはローソンのカフェインレスカフェラテで、これを買うためにコンビニをハシゴした。
最近、このカフェインレスカフェラテに救われている。
わたしはカフェインに過敏で、コーヒーが好きなのに飲むと動機が止まらなくなってしまう厄介な体質なのだ。
その日のコンディションにもよるのだけれど。
ローソンのマチカフェではカフェインレスのカフェラテが飲める。とっても美味しい。大好き。
しかし、カフェインレスのカフェラテをわざわざ頼む人なんてほとんどいないのか、対応してくれた大学生くらいのバイト君は「カフェインレスっていうのは……ええと……」と困っていた。
わたしはお客さんの分際で、レジの横に置いてあるバーコードのついたプラスチックの板(伝われ)を指さして「たぶんこれです」とかついつい指示を出してしまった。さらに困惑された。
ごめんねバイト君。
でも、お姉さんはどうしてもカフェインレスじゃないとダメなんだ。無事に伝わってよかった。
ちなみに、昨日もまた別のバイト君に困惑されたので、お姉さんは指示を出すのにやや手慣れてしまった。
また人を困らせるかもしれないから、次はもっとスムーズに教えよう。
本紹介のつもりが、わたしの食にまつわるエッセイみたいになってしまった。
おわりに
作家さんたちのご飯にまつわるエピソードがたくさん読める、まさに”口福”な一冊。🍽💓
りせ。
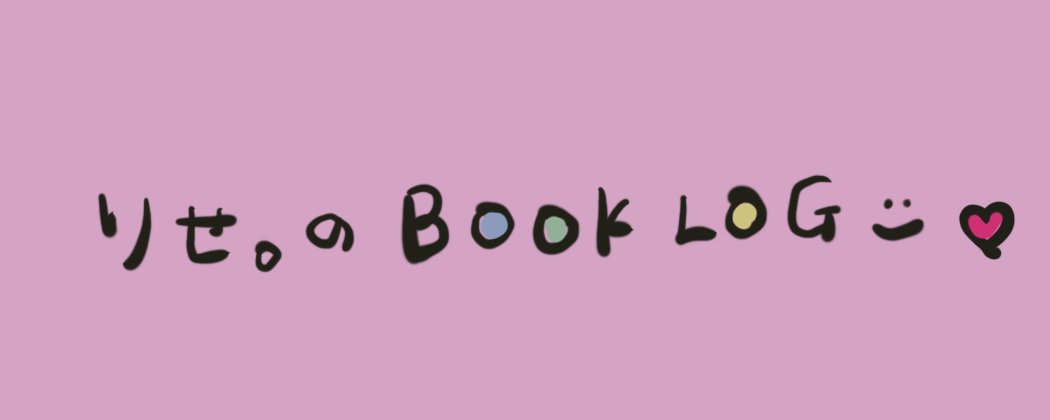

コメント