はじめに
概要
〈われわれ三文文士の多くもまた、及ばずながら言葉に意を注ぎ、物語を紙の上に紡ぎだす技と術に心を砕いている。本書のなかで、私はいかにして「書くことについて」の技と術に通じるようになったか、いま何を知っているのか、どうやって知ったのかを、できるだけ簡潔に語ろうと思っている。〉(本書「前書き」より)
モダン・ホラーの巨匠が苦闘時代からベストセラー作家となるまで自らの体験に照らし合わせて綴った自伝的文章読本。『小説作法』の題名で刊行された名著の待望の新訳版。
巻末には新たに著者が二〇〇一年から〇九年にかけて読んだ本のベスト八十冊を掲載。
小学館文庫
この本を初めて読んだのは大学生2年生か3年生の頃。
もうずいぶん前になるけれど、友達と東京へ旅行に行った時に、渋谷のTSUTAYAで買った記憶がある。
最近読み返してみて、どれだけ勇気を貰ったことだろう。
びっしり付箋が貼ってあって、鉛筆で線が引いてあって、当時の自分が熟読していたことがわかった。
※写真
感想
ものを書くときの動機は人さまざまで、それは焦燥でもいいし、興奮でも希望でもいい。あるいは、心のうちにあるもののすべてを表白することはできないという絶望的な思いであってもいい。拳を固め、目を細め、誰かをこてんぱんにやっつけるためでもいい。結婚したいからでもいいし、世界を変えたいからでもいい。動機は問わない。だが、いい加減な気持ちで書くことだけは許されない。繰りかえす。いい加減な気持ちで原稿用紙に向かってはならない。
中略
ものを書くのは、車を洗ったり、アイラインを引いたりするのとは違う。あなたがこのことを真摯に受け止められるなら、話を続けよう。でなかったら、この本を閉じて、ほかのことをしたほうがいい。
P142
才能は練習の概念を変える。どんなことでも、自分に才能があるとわかると、ひとは指から血が出たり、目が飛びだしそうになるまで、それに没頭する。聞いている者や、読んでいる者や、見ている者がいなくても、それは素晴らしいパフォーマンスになる。
中略
本を読んだり、ものを書いたりするのも、楽器を演奏したり、野球のボールを打ったり、フルマラソンを完走したりするのと同様である。毎日、四時間から六時間を読んだり書いたりするのにあてるべしと言えば、けっこう厳しいと思う者もいるだろうが、しかるべき才能があり、それを楽しむことができるのなら、まったく苦にはならないはずだ。実際にそれを日課としている者も少なくない。その程度は朝めしまえだろう。心ゆくまで読んだり書いたりすることに後ろめたさを感じている方がいるとすれば、私がいまここで許可を与えるので、どうかご心配なく。
読むことが何より大事なのは、それによって書くことに親しみを覚え、書くことが楽になるということである。
中略
読書の習慣は、我を忘れて書くことに没頭できる場所へひとをいざなう。同時に、それは知識を無限大に増加させる。これまで何がなされたか、何がなされていないか。何が陳腐で、何が新鮮か。ページの上で、何が生きていて、何が死んでいるか(あるいは死につつあるか)。
P199~120
私にとって、音楽を聞くのはドアを閉めるのと同じ行為である。それは私を取り囲み、俗世間を締めだしてくれる。書くときに世界を排除したいという思いは、誰にだってあるはずだ。作家は書くことで自分の世界をつくりだしているのだから。
P208
私がものを書くのは自分が充たされるためである、書くことによって家のローンも払えたし、子供たちを大学へやることもできたが、それは結果でしかない。私が書くのは悦びのためだ。純粋に楽しいからだ。楽しみですることは、永遠に続けることができる。
私にとって、書くという行為はときに信仰であり、絶望に対する抵抗である。本書の後半はそういう気持ちから書いた。子供のころよく使った言葉を借りるなら、”必死のパッチ”で書いた。一九九九年の夏、青いヴァンに轢き殺されそうになったとき、私はそのことを知った。
P333
いつだって始めるまえがいちばん怖い。
始めたら、それ以上は悪くならない。
中略
ものを書くのは、金を稼ぐためでも、有名になるためでも、もてるためでも、セックスの相手を見つけるためでも、友人をつくるためでもない。一言でいうなら、読む者の人生を豊かにし、同時に書く者の人生も豊かにするためだ。立ち上がり、力をつけ、乗り越えるためだ。幸せになるためだ。おわかりいただけただろうか。幸せになるためなのだ。
中略
あなたは書けるし、書くべきである。最初の一歩を踏みだす勇気があれば、書いていける。書くということは魔法であり、すべての創造的な芸術と同様、命の水である。その水に値札はついていない。飲み放題だ。
腹いっぱい、飲めばいい。
P357~359
書くという行為に対する勇気をくれた本です。
※写真
おわりに
この本は、「書く」という行為に勇気を与えてくれたきっかけの一冊です。これからも何度も何度も読み返すでしょう。すべての「書く人」へのバイブル。
りせ。
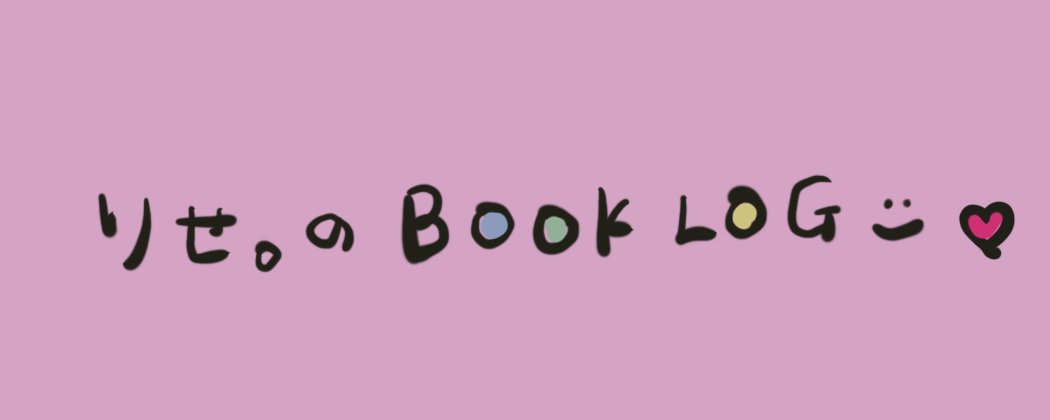

コメント