はじめに
あらすじ
進学校の女子高で、自らを「僕」と称する文芸部員たち。17歳の魂のゆらぎを鮮烈に描き出した著者のデビュー作「僕はかぐや姫」。無機質な新構想大学の寮で出会った少女たちの孤独な魂の邂逅を掬い上げた芥川賞受賞作「至高聖女」。語り継がれる傑作二編が、待望の復刊!
ポプラ文庫
「僕はかぐや姫」に最初に触れたきっかけは、センター試験現代文の過去問で、だった気がする。
当時は絶版になっており、全文読むことはできなかった。
けれど、私はおそらくその前に、松村さんの作品を別の短編集で読んでいて、既にその魅力にとりつかれていた。
今でも、「窓」という短編が大好きで、折に触れては何度も読み返す。
感想
僕はかぐや姫
「産んでと頼んだわけじゃないのに生まれてきて、生きるって決めたわけじゃないのに、人間として生きることさえ選択してもいないのに、女性として生きるって決めつけられて何の選択肢もないなんて、とても理不尽な話だって昔思ったんじゃないかな。『ちょっと待って』って言いたかった。だから、男の子になりたいかどうかはともかく、とりあえず女の子ってことはこっちにおいといてって」
P59
魂を裸で持っている人はいないのだ、と裕生は思った。かつて裕生も尚子もそれをちっぽけな硝子のかけらみたいな感傷に封じ込めていた。そしてそれを剣のように振りかざしたり、そのまぶしさに目をやられたり、掌にじっと握りしめたりしていた。何の役に立たなくても、握りしめた拳をかえって引き裂いたとしても彼女らには大切なものだった。なくすのが、壊すのが、汚すのが怖かった。
かけらを損なう恐れのあるものはたくさんあった。女になること、おとなになること、さまざまな知恵をつけること、何かになじむこと。<僕>が防波堤だった。
P93~94
至高聖所
わたしの中にゆっくりとあの雪の日の共感がよみがえってくる。あるいは炎天下の広場に立っていた真穂。寝息も立てずに眠り続けていた真穂。もうずいぶん前から、彼女の発する弱々しいパルスをわたしのどこかにひそんだ受信機はキャッチし続けていた。解読すればそれは淋しさなのだろう。でもそれは肉親を亡くした淋しさではなくて、淋しいと言って泣くことを淋しいと感じる以前に拒絶してしまったそんな淋しさだ。わたしたちが愛さなければならないのは、そういう自分なのかもしれない。
P203
おわりに
松村栄子さんは、私が好きな作家さんの中でも個人的に思い入れが強い方の一人です。
松村さんのデビュー作である「僕はかぐや姫」も、芥川賞受賞作である「至高聖所」も、独特の感性と抜群の筆力が堪能できる素晴らしい作品なので、ぜひ読んでみてください。
今を生きる高校生や大学生に。そしていつか高校生や大学生だったすべての人達に、読んでほしい一冊です。
りせ。
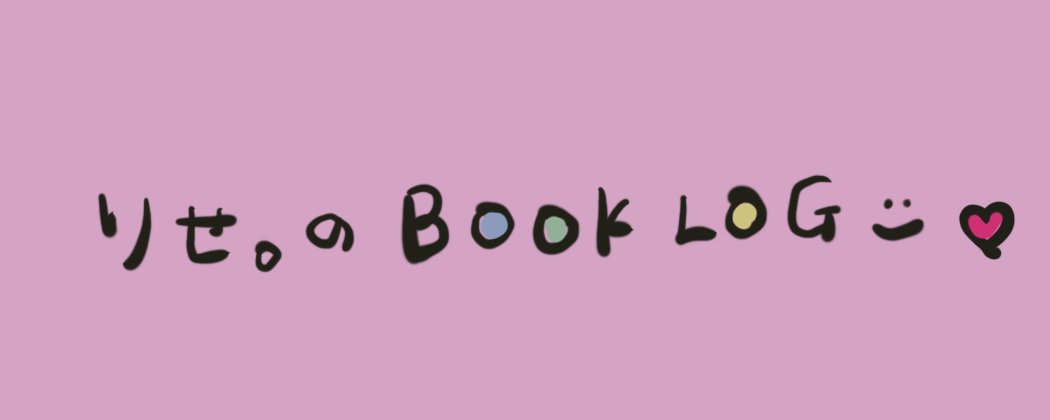

コメント