はじめに
概要
小説、漫画、映画に音楽、舞台まで……少女時代からありとあらゆるエンターテインメントを堪能し、物語を愛し続ける作家の眼にはどんな世界が映っているのか? その耳では、どんな響きを感じているのか? どんな言葉で語るのか? 軽やかな筆致で想像力の海原を縦横無尽に楽しみ尽くす、とびきり贅沢なエッセイ集。
ちくま文庫
私の大好きな作家さん、恩田陸さんのエッセイ集は貴重なので、いつもとても楽しみにして読んでいる。この本も、2005~2010年に書かれた文章をまとめたもので、さまざまな媒体に元のエッセイ(というか本の解説なども多い)が掲載されています。
恩田陸さんはいつしかのエッセイで、エッセイなど自分についての文章を書くのが苦手だ(あまり好きではない?)と書かれていたのも記憶している。だからこそ、より貴重なものと思っていつも拝読するのです。
そんな恩田氏が出したエッセイ集が、『小説以外』というタイトルだったのも当時高校生だった私は心をぶち抜かれて。なんて格好いいんだ!クールなタイトルだ!と思って夢中になって読んでいた、よく通っていたドトールコーヒーで。
私は自分の好きな小説家のエッセイを読むのが大好きなので(作家さん自体のファンになることが多い)、本書でも恩田陸さんがなぜ”一人称ではなく三人称で小説を書くことが多いのか”、など、執筆の本質に迫るような裏側のような部分を少しでも知れるのがとても嬉しいし、一ファンとしてやはり興奮してしまいます。
では、私が個人的に心に刺さった、いくつかの項目をざっくりと引用させてもらいましょう。
感想
「喪失について」
小説は作り物だし、読者の苦しみを肩代わりはできない。だが、私たちにそっと寄り添って、私たちが一人きりではないことを今も教えてくれているのだ。
(ロバート・ネイサン『ジェニーの肖像』、創元推理文庫解説 2005・5)
これはまさに私自身が小説という読み物にずっと救われてきている大きな理由の一つで、誰にも自分の悩みを吐き出せなかった頃、小説の世界に没頭することで孤独感を癒していたのだと思う。10代の頃は特に。
フィクションの世界だからこそ、リアルを生きる私たちに与える影響や力があると、昔からずっと思っていて。
今もずっとその考え方は変わらず私の根本にあるのを感じる。だからこそ、そういう感覚を的確に言語化してくれる恩田陸さんはやっぱりすごいなあ。
深化する
小川洋子さんに関する文章もとても素晴らしいもので、その鋭く美しい分析に、思わずうっとりしてしまった。
特に『猫を抱いて象と泳ぐ』のチェス、あるいはチェスプレイヤーという存在くらい、近年小川洋子的なものは見つからないだろう。『博士の愛した数式』における数学者もそうであったが、彼らの存在のある種のいびつさ、傷ましさ、悲劇性といったものが、小川洋子の求めるモチーフにしっかり収まる。それというのも、小川洋子という作家には全く悲劇趣味がないからである。悲劇をきちんと書けるのは悲劇趣味がない作家だけで、存在そのものが悲劇的であるチェスプレイヤーを描けるのは、現在どう考えてもやはり小川洋子しかいない。
~中略~
『猫を抱いて蔵と泳ぐ」を描いた小川洋子は、小説というもの、あるいは自分の小説が幸福な上澄みとして読まれることをどこかきっぱりと拒絶したように思える。上澄みは、底に沈んだ泥や不純物と元は一体だったのだとこの小説で証明してみせたのだ。
P52 (小川洋子の小説について 『文藝』2009・秋)
「小説が幸福な上澄みとして読まれること」への拒絶。この感覚は、読者側の立場である私自身も理解できる。理解できる、と書いてしまうとそれは違うのかもしれない。でも、似た感覚には確実に覚えがある。
学生時代、手当たり次第に、まるでなにかの真理を追い求める求道者のような気持ちで小説を濫読していた自分にとって、小説とは切実な存在で、単なる『娯楽』以上の意味を持っていた。
だから、小説に対して重たい感情を抱いてしまっているからこそ、「ああ、それ、いい話だよね」とか、「泣けた」とか、そういうインスタントな(?) 物語の消化のされ方には、未だに抵抗感がある。
もちろん、読書はどんな人に対しても開かれているものだし、どんな楽しみ方をしても自由。
でも、小説を書いたり、読んだりすることに、それ以上の意味と労力を見出してしまっている人間からすれば、ファッションの一部のように消費されてしまうのだとしたら、やっぱりそれは乱暴だ、と主張したくなる。
挿絵の魔力
ここでは、恩田陸さんのルーツの1つとして、絵本についてのエピソードが綴られている。
小学校に上がるまでは、絵本の中の世界がそのまま脳内イメージになっていて、つぎはぎになった絵本の絵の世界に生きていたような気がする。
『ちいさいおうち』に流れる、何世代もの長い長い時間。
『せいめいのれきし』の光と影に満ちた荘厳な時間。
『てぶくろ』の、ミクロでいてマクロな生き物の世界。
『ぐりとぐら』の、巨大な卵からできたホカホカのカステラ。
『ももいろのきりん』の、色とりどりのクレヨンがなる木。
毎日毎日繰り返し飽きもせずにページを開き、あげくの果てにはページの外の話の続きを自分でこしらえたり、薄い絵本に不満を抱いて、いつまでも終わらない絵本があればいいのにと夢想していた。
P157
わぁ、わたしも『ぐりとぐら』大好き。
絵本は私も小さい頃から大好きで、親から読み聞かせをしてもらっていた時代から長く愛読してきた。
母親に尋ねたところ、
本に親しむにつけ、だんだん長いものが読めるようになると、少しずつ挿絵が減ってゆき、ついに全く絵のない本を読んだ時にはずいぶん大人になったような気がしたものだった。今では、小説に絵が付いているほうが「イメージを限定してしまうのになあ」と思う。
P158
この成長過程を通ってきた自覚もある。随分と懐かしい気持ちに浸ってしまう。
そして、この中でで言及されている雑誌『詩とメルヘン』が、やなせたかしさんの責任編集でサンリオ社から出ていたのだということは、先日個人的に訪れた『サンリオ展』でサンリオの社の歴史を知り、偶然、存在を認知したところだった。
まさか、それを恩田陸さんが愛読していたとは……!些細な偶然の巡り会い (?) に、勝手に嬉しくなる。
子どもの頃に見ていた絵本の中の世界は、今もなお巨大な背景となって私の頭の中と繋がっているし、その世界をもっと理解したい、味わいたいという願望を満たすために、私は小説を書き続けているのかもしれない。
(晶文社ホームページ 2007・1)
ああ、作家さんのこういう文章を読みたくて、私はエッセイに手を伸ばすのかもしれない。好きな作家さんが、小説を書き続けている理由を一部分でも垣間見るのは、なんとも言えない幸福だ。
恐るべき少女たち
かように、少女たちの奇跡の時間は短い。実際、肉体的にもはっきりと少女の終わりを自覚させられるし、変貌する自分の身体についていけない。
私の言説だが、女性作家に吸血鬼ものや超能力者ものの傑作が多いのは、自分がある時期怪物になっていくような恐怖を味わうからだと思う、やおいものが生まれるのも、変貌しない性に憧憬を抱くからだ。
だからこそ、人はそこに謎を見、神性を見、畏れを抱き、強く惹かれる。
(晶文社ホームページ 2006・6)
恩田作品には、ここで書かれているような「恐るべき少女たち」がモチーフとして出てくることが多い。
私はまさに、10代後半の学生時代に恩田作品にどハマりした身だ。
こういう「少女の終わりを自覚させられる」ことに多くの女性同様、どこか無意識で怯えや恐れを感じていて、だからこそ、逆説的に同年代の美しくも儚い少女たちが出てくる物語に魅了されたのだろう。
もちろん、思春期に偏愛した作品たちは今でも大好きなのだけれど、高校生の頃は本当に切実な気持ちで、まるで縋るようにのめり込んでいた記憶がある。
私もいつか、いやいつかなんて本当はいいたくない、近いうちに、そういう小説を書いてみたい。改めてそう思った。
おわりに
ここで抜粋・引用した部分は本当に一部分で、ほかにもたくさんお気に入りのエッセイがまとめられています。
恩田陸さんの読書史やバックグラウンドを垣間見ることができる、ファンにとっては心躍る一冊。
りせ。
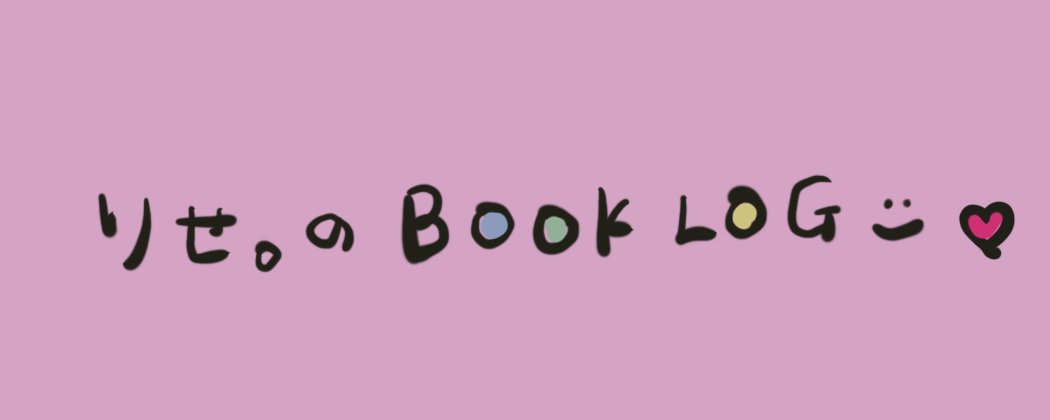

コメント