はじめに
あらすじ
孤児院で暮す五歳の倉折飛鳥は、ある日公園で親切な青年と出会う。二年後、引き取られた家での虐げに耐えかねて逃げ出した彼女を助けたのは、かつての青年、滝杷祐也だった。彼は周囲の反対を押し切って飛鳥を手元に引き取る。その親友の近端史郎、家政婦のトキらに見守られる中で、頑なな飛鳥の心は徐々に変化を遂げるが、ある毒殺事件を切っ掛けに、人々の思いは錯綜を深めてゆく……。マルシャークの童話「森は生きている」を軸として、雪の街を舞台に、孤独な少女とある青年の奇跡的な出会い、そして二人の葛藤の歳月を描く、著者の代表作。
創元推理文庫より
この本に出会ったのは、年下の男友達におすすめしてもらったことがきっかけ。
5年前くらいかな。ものすごく読みごたえのある一冊で、夢中になって読んだ記憶がある。
今回、感想をざっくりとまとめようと思い軽く読み返し始めたら、また止まらなくなってしまい、一気に読破してしまった。
印象に残った部分
もし可能ならばこの瞬間が、瞬間ではなく停止してしまえばいい。私はこのままが一番幸せなのだ。時間は人間を成長させる。成長は新しい生活を循環させる。私は新しい生活など欲しくない、祐也さんが結婚するのもいやだし私自身が大人になって知らない男の人と結婚するのはもっといやだ。何故このままではいけないのだろう? 時間の動きは大自然が操作するのだ。私がどんなにあがいても止めることはできない。
中略
しかし――やはり私は時間を止めたいと思う。自然の摂理に逆らっても祐也さんとの生活を守りたい。
p119
飛鳥が祐也に珍しく、勇気を出して甘えるシーン。
「時間は人間を成長させる。成長は新しい生活を循環させる。」
当たり前のような事実なのに、この物語のなかのフレーズとして読むとき、なんだかとても、胸が苦しいくらいの感傷的な気持ちに駆られる。
何があっても、時間は止められないし、人間は前に進まなければならない。
そのことに、10代の頃は漠然とした不安感を覚えたり、悩んだりしていたことを思い出す。
まだ成長途中でやわらかい飛鳥の繊細な気持ちを、守ってあげたくなる。
人間も自然の小さな置き物だという。人間に心があるのなら山に心がないと誰が言い切れるか。残雪が私に語り涙をこぼし愛をつぶやかないと誰が言い切れるか。本当に気持を通わせることができるならそれは人間界の言葉は用いないだろう。私たちの便利のために作り出した道具など必要ではない。自然の意志はもっと高潔で尊い手段を与えてくれたはずだ。私たちはそれを忘れたために山や空や雪と話せなくなった。植物も動物も昆虫たちも仲良く暮しているのに人間だけが仲間はずれになってしまったのだ。満たされない心の空間は自然の位置するものなのかもしれない。山と空と、植物や動物たちと、すべての生命あるものたちと心を通わす可能性を秘めた聖地ではないのか。人間同士が理解し合う野ではなく、大自然と分ち合うためのものではないのか。
p136
この小説は、主人公である飛鳥の成長物語や内面の心理描写がメインだと思われがちかもしれないけれど、こういった自然に対する描写も本当に美しく、心を打たれる。
私は田舎育ちで、今まで住んだことのある土地もすべて雪国だから、自然に対する敬意が生まれる気持ちはとてもわかる。
人間の存在なんて、大自然から見ればなんてちっぽけなものなんだろう、と何度も思いながら育ってきた。
「森は生きている」という童話が重要なモチーフになっていたり、飛鳥にとっての「神聖」である祐也が「四月の精」になぞらえられているように、作中では自然へ向けるまなざしが一貫していて、読んでいて心地よさすら感じる。
祐也になんとなく人間味が薄く感じるのも、神聖なる自然のモチーフ的存在という解釈なら納得がいく。
飛鳥が自然に頭を垂れるように、祐也を尊敬し慕っているという視点からの描写なのだから。
どんよりと曇った天から純白の雪がおりて来る。空の精がおりて来るのだ。両手をのべると二、三片が手のひらに舞い立った。手が冷たくなっているので溶けなかった。口をききたい。雪の言葉を理解したいと思った。私は雪の声を聞いた。
裏切りがあるから信じ、崩れるから積むのでしょう、溶けるから降るように。
降ることも溶けることも自然の意志で行為は同じ。なぜ積むのが大切で崩れるのが哀しいの? 信じることよりも裏切ることの方がなぜいけないの? 同じ心から生れたものに正しいとか正しくないとかってそれはどういう意味なの? 自分たちで作り出した感情と行為に苦しむことが理解できない。雪はみんな白い。人間もみんな心を持っている。何もどこも誰も変ってやしないのに。すべてが同じで繰り返すのだから淋しい目をしないで――。
でも、私はやっぱり雪がうらやましい。短くてもいいから白く生きたいと思った。雪に生れたかった。
p219 ~220
自分の生育環境や経験から他人をどうしても信用できず、他人に自分のことを相談したり心を打ち明けたりできない飛鳥は、激しく心が傷付き揺れ動いた時、こうして雪と話したいと願い、雪の声を聞く。
「短くてもいいから白く生きたい」。
飛鳥の純白で真っすぐな精神性が、眩しくて沁みる。
「あなたのころが気がかりなの、大人になりかけている大事な時期には誰かが手を添えてやらなければならない、どんなに優しくてもそれは男の人では届かないものなのよ。動揺しやすい心に次から次へと襲うものがあれば、せっかくまっすぐに伸びようとしている芽を枯らせてしまうでしょう。だから、せめて力が及ばなくても精いっぱい慰め一緒に悩んでくれる人に打ち明けて素直な子になってちょうだい」
体内のすみずみに厚子さんの声がしみた。そしてゆっくりとやわらかい胸に顔を埋めた。きっと強い素直な生き方をすると誓い、撫でられる快さをかみしめた。
p205~206
飛鳥のことを気にかけ寄り添う大人の女性、厚子の言葉は、同年代にあたる自分であってもそう思うだろうと、とても共感した。
昨今の世の中は核家族化しており、ご近所付き合いのような関わりも希薄になっているけれど、自立する前の年齢の子たちにはこういう存在が絶対に必要で、そうでないと心がねじ曲がり折れやすくなってしまう。
自分も厚子のようなまなざしを若い子に対して持っていたいと思う。
「
飛鳥、人の運なんてこんなものなんだよ。些細なことが受け取る側に邪推があればどんどん毒となって体に回ってしまう。物事はいつも同じ速度と冷たい事実だけなのだ。それを動かす人間によって、右へ左へ、昇るか落ちるかに分かたれてしまう。
中略
どのような事態に置かれても、まず自分を信じて確立することだ。それに沿ってまわりの意見や思惑をとり入れてゆくのが本来の姿だと思う」
p375~376
「どのような事態に置かれても、まず自分を信じて確立すること」。
これは、言葉にするのは簡単でも、実際にはすごく難しいことだ。
私自身も感情に流され、物事を偏った視点で見てしまい、早計な判断をして後々間違ったなあと後悔することがある。
受け取る側の心理的状況によって、同じ物事でも良い方向へ向かう場合もあれば、逆のこともあるということ。
できるだけフラットな状態で物事を判断し進めていくことは、生きていくうえで重要な姿勢なんだと思った。
感想
北海道札幌市を舞台にした、美しい文学的なミステリ。
私は高校生の頃から札幌という土地に漠然とした憧れがあり、進学先の大学も選んだので、個人的にとても思い入れが深い。
作中でも重要な場所となっている「大通公園」はよく友達と訪れていたし、馴染み深い場所だった。
そんな場所で、運命的な出会いを果たす飛鳥と祐也。
古い時代のことはほとんどわからないけれど、すごくロマンチックで素敵な舞台背景に感じて、いつか二人に思いを馳せながら大通公園を歩きたいと思った。
私自身も、飛鳥ほど強情ではない(と思う)けれど、元・多感な少女として共感できる描写が多くあり、周囲の登場人物もそれぞれに魅力的で、心が激しく動かされる。
読むのにもハイカロリーを消費するような、エネルギーに満ちた物語。
孤児としてさまざまな経験をしなければならず、心に深い傷を負いながらも、懸命に生きていこうとする飛鳥を応援したくなる。
そして、自分自身も背筋を伸ばして、厳しい現実や対人関係に挑もうと思える。
本棚に必ず並べておいて、折に触れては何度も読み返したくなるような大切な一冊。
おわりに
たとえどんな境遇にあっても、希望を捨てずに強かに生きてゆく勇気を貰える。幻想的で文学的な非常に奥深い一冊です⛄💙
りせ。
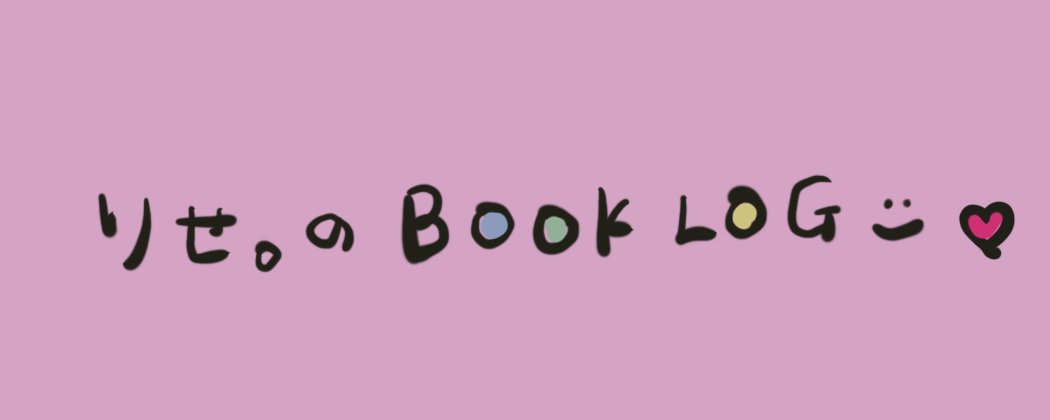

コメント