はじめに
あらすじ
あなたと共にいることを、世界中の誰もが反対し、批判するはずだ。わたしを心配するからこそ、誰もがわたしの話に耳を傾けないだろう。それでも文、わたしはあなたのそばにいたい――。再会すべきではなかったかもしれない男女がもう一度出会ったとき、運命は周囲の人を巻き込みながら疾走を始める。新しい人間関係への旅立ちを描き、実力派作家が遺憾なく本領を発揮した、息をのむ傑作小説。
単行本より
印象に残った部分
二章 彼女のはなし Ⅰ
わたしのお母さんが明るいうちからお酒を飲むことについては、以前からクラスでささやかれていた。気が向いたときにしか料理をしないことも、たまにアイスクリームが夕飯になることも、子供には過激とされる映画を家族で観ることも、お父さんとお母さんがキスをすることも、それら諸々すべてがクラスメイトには信じられないことだったようだ。
お母さんの爪がいつもきれいな色であることすら、いけないことのように同じマンションのおばさんたちが話していた。どうしてだろう。わたしは綺麗なものが大好きだ。お父さんもお母さんもそうだ。みんな綺麗なものが嫌いなんだろうか。変なの。
P20~21
でも本を読むだけなら、あの男の人は喫茶店にでもいけばいいのだ。だって大人は子供とちがって好きなところにいける。わたしは子供だから、あなたの席はここ、と決められたところから動けない。ああ、もしかして、あの男の人もどこにも居場所がないのかな。
P27
所在なさげに公園のベンチで長い時間を過ごす「文」と、更紗の魂が邂逅し、共鳴し始める瞬間。
物語のはじまり。
三章 彼女のはなし Ⅱ
わたしは、どうか文が幸せでありますようにと願っている。文を取り返しのつかない苦しい場所へと押し出す手伝いをしてしまった自分が、文の幸せを願っているなんてちゃんちゃらおかしい。けれど願っているのだ。心から、今、幸せでいてくれますようにと。
なのに同じ強さで、わたしのことを忘れないでほしいと願っている。文の記憶の中で、わたしは不快な存在になっているだろうけれど、なのに、それでも、文の心の中から消し去られるのは嫌だった。度し難いと思いながら、今日も問いを投げている。
——ねえ文、わたしのことを覚えてる?
P108
なにも知らないくせにとわたしはひどく腹を立て、一方で不安に駆られた。わたしを知らない人が、わたしの心を勝手に分析し、当て推量をする。そうして当のわたし自身がわたしを疑いだし、少しずつ自分が何者なのかわからなくなっていった。長い時間をかけて、わたしの言葉は誰にも通じなくなっていき、それを解読できるのは、もはや文だけだと思っていた。
P124
自分自身が自分自身のことをわからなくなっていく、見失っていく感覚。
これはとてもよくわかる。
わたしもよく、人に自分の話を打ち明けた時、なにか意見を言われたとき、だんだん、自分のなかの自我が危うくなっていく感覚を味わうことがある。
どこまでが人の意見や考えで、どこからが自分の気持ちなのか。
自分の考え何て本当に存在するのだろうか。
記憶は共有する相手がいてこそ強化される。わたしはこれから、たったひとりであの二ヶ月間を抱えていくことになる。幸せなほど重みを増すそれに、わたしは耐えられるだろうか。思いからもういらない。そう言って、ぱっと手放せれば楽なのに。
——重いことはそれだけで有罪だわね。
——だって手をぶらぶらできないじゃない。
そう言って、お母さんは見事にわたしを手放した。きっと今も手をぶらぶらさせながら歩いているのだろう。わたしにはそれができない。お母さんがうらやましくてたまらない。子供のころは早く大人になって、お父さんのような人と結婚して、お母さんのように楽しく暮らすことを夢見ていた。あのころ身近だった夢が、今は触れられないほど遠く感じる。
P128
なんの力もない、無責任な言葉しか浮かばなかった。どんな痛みもいつか誰かと分けあえるなんて嘘だと思う。わたしの手にも、みんなの手にも、ひとつのバッグがある。それは誰にも代わりに持ってもらえない。一生自分が抱えて歩くバッグの中に、文のそれは入っている。わたしのバッグにも入っている。中身はそれぞれちがうけど、けっして捨てられないのだ。
P220
わたしたちは親子ではなく、夫婦でもなく、恋人でもなく、友達というのもなんとなくちがう。わたしたちの間には、言葉にできるようなわかりやすいつながりはなく、なにも守られておらず、それれひとりで、けれどそれがお互いをとても近く感じさせている。
わたしは、これを、なんと呼べばいいのかわからない。
P239 ~240
おわりに
本屋大賞受賞作。どんな人にも読んでほしい傑作です。
りせ。
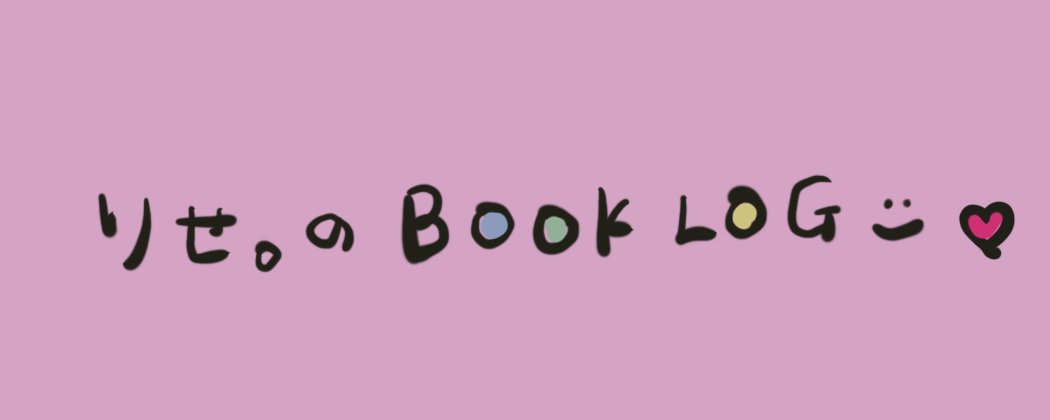

コメント